保険。皆さん、保険には加入されていますか?

我が家はバッチリ加入済みでございます。独身の時は、保険のホの字も知らなかった私ですが、結婚・出産を機に怒涛の如く保険に加入した過去を持つ我が家。
今回は、家計を最も圧迫しやすい・また節約のしがいがあるーと言われている「保険料」について書いてみます。
我が家の保険加入種類

- 生命保険
- 収入保障保険
- 医療保険
- がん保険
- 学資保険
- 自動車保険
- 自転車保険
- 地震・火災保険
実に8種類!加入しています。

①:生命保険
我が家は死亡保険の補償を確保しつつ、貯蓄もできるタイプを契約しています。

補償内容
- 旦那死亡時・・・500万円(終身)
- 旦那が定年退職後解約・・・400万程の返戻金。
低解約返戻金終身保険なので、保険料が比較的安い&保険内容が手厚い!
低解約返戻金保険とは?
保険料支払いの途中で解約すると、今まで払った金額の70%程しか戻ってこない。しかし、保険料をすべて払い込むと、解約返戻率がぐぐぐっと上がる保険の種類の事。
- 途中で解約…70%前後の返戻金。
- 支払い済み後の解約…120%~以上の返戻金。
月々の支払…8385円(年払いにして少し安くなっています)
掛け捨てタイプではなくて、貯蓄型なので月々8385円を支払っても貯金している感覚でいられるのがGOOD!また旦那がいくつで死亡しても一律500万貰えるのも超GOOD(←おい)
②:収入保障保険
旦那が死亡または働けなくなった場合に、月々お金が貰える保険。
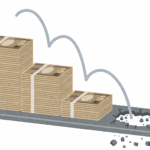
補償内容
- 死亡・働けなくなった場合・・・月々10万円
旦那が死亡・働けなくなった場合に月々10万円貰える保険です。定年退職するまでの期間契約していて、万が一の場合はその間ずっとお金が貰える仕組み。
収入保障保険のため、比較的安い値段で手厚い保険となっています。
収入保障保険とは?
死亡保険金を年金形式で受け取るタイプの生命保険。 年数経過とともに貰える保険金額の総額が一定額づつ減少していく。
【例】旦那60歳まで契約
- 旦那が死亡30歳⇒30年間貰える。
- 旦那が死亡60歳⇒5年間貰える。(最低支払5年保証付きの場合)ない場合は0年・全くもらえない。
月々の支払…3805円(年払いにして少し安くなっています)
旦那が20代の頃、健康優良体割引で加入した保険。マイホームを購入したので(団信加入済み)こちらの収入保障保険は解約してもいいかなぁ~と思っているのですが月々3800円で10万円の安心が買えるのも悪くないかな~と解約できずにいます。貰える年数が減ってくる、旦那50代くらいあたりになったら解約しようかな。
③:医療保険
旦那・私ともに加入。子供は未加入。

補償内容
- 旦那・・・入院5000円/1日
- 私・・・入院5000円/1日
旦那・私共に1日5000円補償の医療保険に加入しています。
月々の支払い・・・二人合わせて5007円(年払いにして少し安くなっています)
医療保険は必要ないという意見が多いですが(高額医療費制度があるため)神経質な私は入院は個室じゃないと治るものも治らない!という理念(?)の元、加入しております。先進医療を受ける時に一時金が出るのも安心材料。また払い込み終えると終身保険として残るタイプなので解約せずにいます。
④:がん保険
旦那が加入。
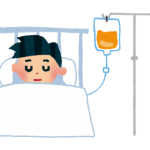
会社が全額負担してくれているがん保険。そのため補償内容がイマイチ不明なのですが、がんになったら保険が下りるようです。
⑤:学資保険(低解約返戻金保険)
息子の学資保険。

息子の将来のための貯蓄型保険。息子が生まれた頃は条件のいい学資保険がイマイチなくて、いわゆるTHE!学資保険には加入しませんでした。代わりになる「低解約返戻金保険」に加入。①の生命保険と同じですね。
学資保険は親が万が一の場合、保険の契約内容の補償&支払い免除特約が付いているのがほとんどですが、低解約返戻金保険でも契約者を親にすれば、万が一の死亡時保険金がもらえます。
学資保険より低解約返戻金保険の方がお得だった理由(2010年ごろ当時の話)
- 学資保険・・・払い込み15年で解約後、約180万円程度の返戻金。(親が死亡した場合180万貰える)
- 低解約返戻金保険・・・払い込み15年で解約後、約200万。解約しなければしない程返戻金が増えていく。(親が死亡時350万貰える)
補償内容
- 親が死亡時・・・350万。
- 息子が中3・・・約200万返戻金。その後は1年で2万ずつ増えていく。
今は条件のいい学資保険があるのかもしれませんが、学資保険やこども保険といった名前にこだわらないでも代わりになる、条件のいい保険はあると思うので調べるといいかもしれませんね。
月々の支払い・・・10879円
子ども手当から支払う予定でしたが、今のところ旦那の給料から支払っています。子ども手当は貯金中。
⑥:自動車保険
我が家は旦那が車通勤のため、自動車保険は慎重に選んでいます。

補償内容
- 対人賠償保険・・・無制限
- 対物賠償保険 自己負担額・・・無制限・自己負担なし
- 人身障害保障・・・1億
とりあえず相手側に対しての補償は最高額に設定。自身の補償は1億・同乗者は対象外にすることによって保険料を少し抑えています。
年間の支払い・・・50300円
我が家は自動車保険はインターネット自動車保険で有名な「SBI自動車保険」一択です。SBIが一番安くて補償内容がいいと思う。
⑦:自転車保険
家族3世代まで有効な自転車保険に加入。

補償内容
- 賠償責任保険金額・・・最高1億
相手にけがをさせてしまった場合に最高1億円の保険が下りる。自身のけがに対しては
- 入院保険金・・・5000円/1日
小学生息子が自転車に乗り出したので加入。楽天カードを持っている人限定の格安プランで加入させてもらってます。家族3世代まで保証されるのもGOOD!
月々の支払い・・・500円
500円で3世代まで保証されるのでとってもお得だと思っています。自転車保険は単独で入るより、何かの保険のオプション・私のように楽天カード会員限定で加入できる保険などで入った方がお得のような気がします。
⑧:地震・火災保険
マイホームを購入したので加入。

補償内容
- 火災・・・3000万(家財特約付き)
- 地震・・・1500万。
マイホームを購入で避けては通れないのが、火災・地震保険。我が家ももちろん加入しました。
保険料:火災保険(一括払い)&地震保険(5年払い)・・・69万980円
地震保険は5年後また支払う予定です。
保険料 年間支払い総額
以上が30代夫婦&小学生1人=3人家族の加入保険でした。全ての保険の金額を年間と月別に計算すると・・・
- 生命保険・・・10万623円
- 収入保障保険・・・4万5658円
- 医療保険・・・6万95円
- がん保険・・・会社負担
- 学資保険・・・13万548円
- 自動車保険・・・5万300円
- 自転車保険・・・6000円
- 年間 ・・・39万3224円。
- 月換算・・・約3万2768円。
【その他】
- 地震・火災保険・・・69万980円
我が家の月々の保険料支払い金額は「約3万3000円程」という結果になりました。
保険料支払い 平均額はいくら?
次に気になるのが、他のご家庭の保険料の支払金額はいくらくらいなのか?ということ。生命保険文化センターが実施した「生活保障に関する調査」におおよその年間払込保険料の平均額が記載されていました。
【保険料支払い年間総額平均】
- 男性…平均24.1万円/年
- 女性…平均18.2万円/年
ということは、男女合わせての年間払込保険料は42.3万円/年。月に直すと【約3万5000円】
我が家の保険支払額は3万3000円/月なので・・・↓


我が家は2000円程ですが、平均より勝ちました(←何の戦い?)保険の雑誌とか買いまくって勉強してから契約した甲斐があったわ。
我が家の勝因 4つのポイント(偉そうですみません)
- 旦那が20代の若いころに加入を済ませた⇒契約者の年齢が若ければ若いほど保険料が安い。
- 保険料が変わらない保険を選んだ⇒加入時の保険料のまま続けられる。
- 保険の窓口で見積もり比較した⇒複数のお店で見積もりをしてもらうことにより、競争意識の中より良い商品を勧めてくれた。
- 保険辛口レビュー雑誌を買った⇒事前調査・とっても大事。保険の窓口でも知識があると変なものを勧められない。
保険料を抑える 節約術。
我が家の加入保険内容&保険料 (年額)まとめ
- 生命保険・・・死亡500万・貯蓄型/10万623円
- 収入保障保険・・・死亡月10万・掛け捨て/4万5658円
- 医療保険・・・入院5000円・終身/6万95円
- がん保険・・・会社負担
- 学資保険・・・死亡350万・貯蓄型/13万548円
- 自動車保険・・・無制限補償/5万300円
- 自転車保険・・・最高1億補償/6000円
保険料を安くするコツ
- 年齢が若いうちに加入する。1歳の違いでも保険料に差が出る。
- 保険料が変わらない商品を選ぶ。
- 貯蓄型と掛け捨て型を上手に選ぶ。
- 学資保険より低解約返戻金保険の方がお得な場合も。
- おすすめは収入保障保険!段々と貰える金額が減っていくタイプのためお安い保険料で手厚く保証してくれます。
- 自転車保険はオプション加入を狙う。
事前調査する
保険についてある程度事前調査をする。
ステップ1:まずはとりあえずネットから無料見積もりしてみる。
インターネット上から保険の無料見積もりをしてみましょう。加入したい保険と年齢を入力するだけで大体の見積金額が分かります。
ここがGOOD!
- インターネットで各種保険の無料見積もりが出来る。
- 複数の保険会社の商品が一括見積できて便利。
- とりあえず見積もりだけしたい人向け。
ステップ2:加入するときは保険代理店を複数比較検討する。
実際に保険に加入する際は、保険代理店を利用すると便利です。
代理店を利用する利点!
- 話しながら希望の保険を調べてくれる。そして無料。
- 複数の店舗を利用すると、よりメリットのある保険が分かる。
- 面倒な手続きはすべてプランナーさんがやってくれる。
- 加入しなくてもOK。
代理店を利用するには
店舗に赴くタイプとプランナーさんが自宅に来てくれる・またはファミレスなどで落ち合うタイプがあります。全国対応で店舗・自宅訪問・好きな場所で面談が一括で検索できるサイトを利用すると、簡単に予約することができます。

まとめ
一口に保険と言っても色々な種類の保険があり、また補償内容も保険料も本当に様々。これから加入される方は事前調査をする・よく分からないまま加入された方は見直しをしてみるといいかもしれませんね。


